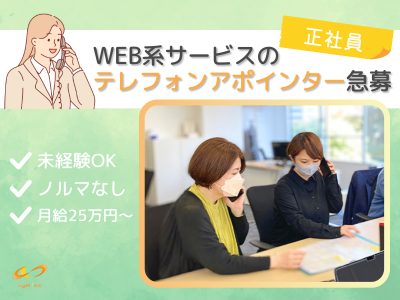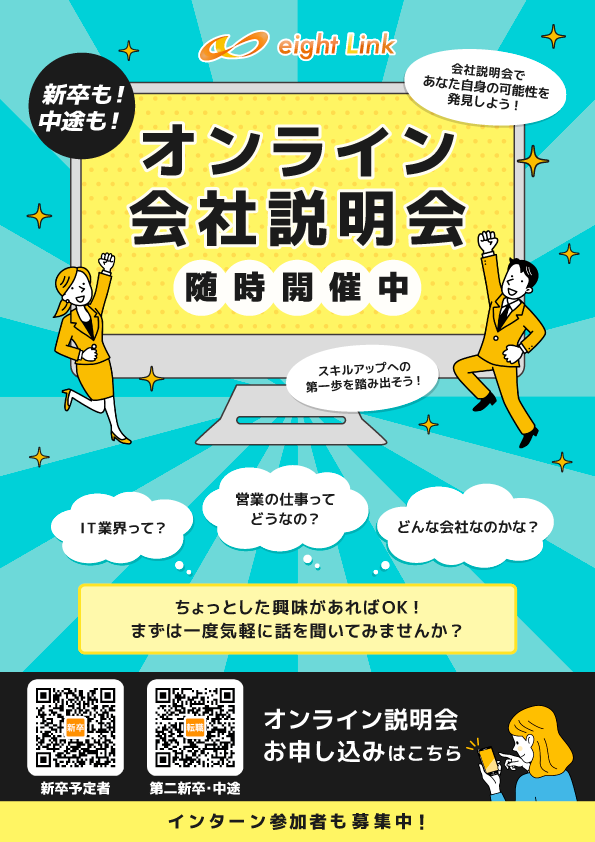「新卒 離職率」というワードを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
近年、新卒の3人に1人が入社後3年以内に会社を辞めているというデータが話題になっています。
SNS上でも「1年で辞めたい」「もう限界」といった声が溢れ、新卒で働き始めたばかりの若者たちが悩みを抱えている現状が浮き彫りになっています。
そこで本記事では、最新の新卒離職率データや実際に辞めたくなる理由を紐解きながら、離職率の高い会社を見抜くコツや「辞めたい」と感じたときにどう動くべきかまでを徹底解説します。
「辞めたいと思うのは甘え?」と悩んでいるあなたへ、今後のキャリアを前向きに考えるヒントをお届けします!
1.「新卒の3人に1人が3年以内に離職する」と言われる時代
「新卒で入った会社は3年続けろ」と言われていた時代は、もう過去のもの。
今や新卒の3人に1人が3年以内に離職する時代になりました。
SNSを覗いてみると、「1年で辞めたい」「もう限界」といった投稿も珍しくありません。
新卒で頑張って働きはじめたものの、理想と現実のギャップに苦しむ人が増えているのです。
本記事では、データやリアルな声をもとに「なぜこんなに離職率が高いのか?」「辞めたくなる理由は何か?」を深掘りしつつ、今後のキャリアの選択肢についてもお伝えしていきます。
2.【最新データ】新卒の離職率は本当に高い?
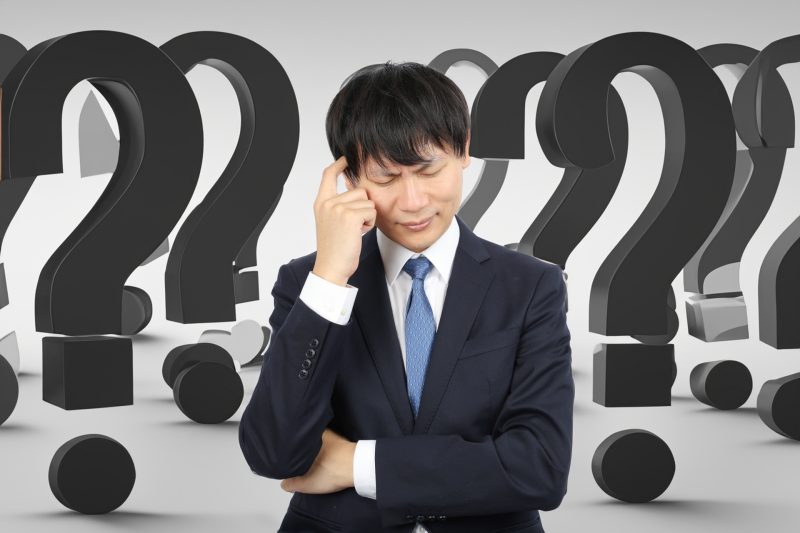
まずは、「新卒の離職率って本当に高いの?」という疑問に答えるべく、実際のデータを見ていきましょう。
厚生労働省の統計をもとに、学歴別・業種別の離職率や、コロナ禍以降に見られる働き方の変化についても詳しく解説していきます。
2-1. 厚労省の統計をチェック
厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の離職状況」調査によると、以下のようなデータが出ています。
- 大卒:3年以内の離職率 約32%
- 短大・高専・専門卒:3年以内の離職率 約40%
- 高卒:3年以内の離職率 約37%
つまり、大卒であっても約3人に1人、短大・専門・高卒ではさらに多くの人が最初の会社を離れているのです。
さらに業種別に見ると、小売業や飲食業、福祉業界などで特に離職率が高い傾向があります。
| 業種 | 3年以内・離職率 |
|---|---|
| 宿泊・飲食サービス業 | 約50% |
| 教育・学習支援業 | 約40% |
| 医療・福祉 | 約38% |
| 情報通信業(IT系を含む) | 約30% |
このように、業種によってもかなり差が出ることが上記の表でわかります。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html
2-2. コロナ以降の傾向変化
コロナ禍を経て、働き方や価値観にも大きな変化がありました。
- フルリモート・ハイブリッドワークの普及
- ワークライフバランス重視
- 終身雇用よりキャリアアップ志向
こうした流れのなかで、「今の会社にずっといなきゃいけない」「3年以上は勤めなければならない」という発想自体が薄れています。
また、“第二新卒”という枠が市民権を得たことで、早期転職のハードルがかなり低くなったのも特徴です。
3年以内の転職=ネガティブ」ではなく、スキルアップや環境改善を目的とする前向きな転職として捉えられる時代になってきたのです。
3. 新卒が辞めたくなる理由とは?
次に、なぜ多くの新卒が「辞めたい」と感じてしまうのか、その理由に迫ります。
人間関係や業務内容のギャップなど、リアルな声をもとに、具体的な要因と背景をひも解いていきましょう。
3-1. 実際によく聞く理由
新卒が「もう辞めたい」と感じる主な理由には、以下のようなものがあります。
- 人間関係/社風が合わない
パワハラ気質な上司、陰湿な派閥争いなど - 想像と違った業務内容
聞いていた仕事内容と実態がかけ離れている - 残業・休日出勤の多さ
ワークライフバランスが取れない - キャリアが見えない不安
成長実感が持てず、将来のビジョンが描けない
特に、人間関係の問題は退職理由の上位常連です。
また、「やりがい重視」と言われる世代ですが、ブラック体質の会社では“やりがい搾取”のような状況に陥ることもあります。
3-2. ミスマッチが起きる背景
では、なぜこんなにミスマッチが起きるのでしょうか?
- 情報不足のまま入社してしまう
忙しい就活スケジュールのなかで、深い企業研究ができなかった - インターンや説明会での「企業の見せ方」の課題
企業側が“理想的な一面だけ”をアピールしてしまい、現場とのギャップが大きくなる
これらの要素が重なると、入社後に「こんなはずじゃなかった…」と感じることになるのです。
4. 離職率の高い会社を見抜くチェックポイント

「できるだけ早く辞めたくない!」そう思うなら、最初から離職率の高い会社を避けることが重要です。
ここでは、面接や説明会で注意すべきポイントや、クチコミサイトを活用した企業リサーチのコツを紹介します。
4-1. 面接・説明会で注目すべき質問やサイン
離職率の高い企業には、面接や説明会の段階でいくつか「違和感」を感じるサインがあります。
ここでは、特に注意したいポイントを具体的に紹介していきます。
■ やたら“やりがい”を強調してくる
「大変だけど成長できる」「若いうちから責任ある仕事ができる」といった言葉を繰り返す企業には注意が必要です。
もちろん、やりがいや成長を重視する文化自体は悪いものではありません。
しかし、「成長」や「やりがい」ばかりを強調し、働き方や労働条件に関する具体的な説明がない場合は、裏を返すと「労働環境が厳しい」「人がすぐ辞めるから若手に負担がかかっている」といった現実が隠れている可能性
特に、
- 「体力勝負だよ!」
- 「最初は根性で乗り切るしかない!」
といった“根性論”が出てきたら要注意。
本当に良い会社なら、成長だけでなく「安心して働ける環境づくり」にも触れるはずです。
■ 社員の平均年齢が若すぎる
若い社員が多い職場は、活気があって魅力的に見えるかもしれません。
しかし、社員の平均年齢が極端に若い場合、「年齢が上がる前に辞めてしまう」「長く働き続ける人が少ない」といった定着率の低さが隠れていることもあります。
特に、
- 30代以上の社員がほとんどいない
- 管理職も20代半ば〜後半ばかり
という場合は、慎重に見極めた方が良いでしょう。
面接中に「社員の平均勤続年数」や「30代・40代の働き方」について質問してみると、企業の実態が垣間見えるかもしれません。
■ 離職率を聞いても明確な答えが返ってこない
面接で「離職率はどのくらいですか?」と聞いたときに、はぐらかされたり、笑ってごまかされたりする場合も要注意です。
- 「勢いでやってるから、あんまり気にしてないね!」
- 「うちは合う人はすごく合うんだよ!」
など、具体的な数字を出さずにポジティブっぽい返答だけをしてくる場合、離職率が高いことを隠したい気持ちが見え隠れしている可能性があります。
一方、良い会社は
- 「直近3年では〇〇%です」
- 「業界平均と比べるとやや低めです」
といった具体的なデータや客観的な説明を用意しています。
「離職率」以外にも、
- 「最近の中途入社の数」
- 「社員の平均勤続年数」
などをセットで聞いてみると、さらに企業の体質を見抜きやすくなります。
面接は企業側があなたを選ぶ場であると同時に、あなたが企業を選ぶ場でもあります。
少しでも「この会社、なんか変だな」「違和感があるな」と感じたら、その感覚は無視しないこと。
たとえ内定をもらっても、無理に受ける必要はありません。
自分の未来を大切にするために、慎重に見極めましょう。
4-2. クチコミサイトの活用方法
企業の内情を知るために、クチコミサイトも活用しましょう。
- openwork
- 転職会議
- ライトハウス(旧カイシャの評判)
これらのサイトでは、実際に働いている(いた)人の声がチェックできます。
見るべきポイントは以下。
- 評価が異様に高い or 低い場合、偏っていないか
- 最新のクチコミがあるか(古すぎる情報は参考になりにくい)
- 同じような不満(例:人間関係・労働時間)が繰り返し出ていないか
うまく活用すれば、入社前にリスクを回避できる可能性が高まります。
5. もし「辞めたい」と思ったら?
もし今、あなたが「辞めたい」と感じているなら、それは決して悪いことではありません。
この章では、辞めるかどうか悩んでいるときに知っておきたい考え方や、実際に行動する前にできることを紹介します。
5-1. 辞める=悪じゃない!視点の転換
「すぐ辞めたらダメ」「とりあえず3年は耐えろ」「石の上にも3年」
そんな言葉を真に受けて苦しむ必要はありません。
キャリアは一本道ではなく、いくつもの分岐点があっていいのです。
そして今の時代、3年以内に転職しても不利にならないケースが多くなっています。
- 第二新卒市場が活性化
- 柔軟なキャリア形成を歓迎する企業が増加
- 転職エージェントも「ポテンシャル採用」を推進
つまり、「辞める=逃げ」ではなく、未来を切り拓くための一歩だという捉え方ができるのです。
5-2. 辞める前にできること
「もう辞めたい」と感じたとき、すぐに退職届を出す前に、できるアクションを試してみることも大切です。
視野を少し広げるだけで、意外な活路が見つかるかもしれません。
■ 社内異動や相談制度を活用する
まずは、今の部署やチームでの悩みが「異動」で解決できないかを検討してみましょう。
実際、
- 上司が変わった
- 配属先が変わった
- 働き方がリモート中心に切り替わった
など、小さな環境の変化によって、人間関係や仕事の負担がぐっと改善したケースはたくさんあります。
最近では、多くの企業が「社内公募制度」や「キャリア面談制度」などを設けており、部署異動のチャンスを開いているところもあります。
特に、大手企業では社内ジョブチェンジが積極的に行われている場合もあるので、「辞める」前に一度、社内リソースを最大限活用できないか相談してみるのも一つの手です。
異動が難しくても、産業医相談や人事相談窓口を活用することで、業務負担の軽減や配慮を受けられる可能性もあります。
■ 第三者の視点を取り入れる
「辞めたい」という気持ちで頭がいっぱいになっていると、冷静な判断ができなくなるものです。
そんなときは、第三者の視点を取り入れることがとても大切。
- 信頼できる先輩社員
- 転職経験者(OB・OG訪問でもOK)
- キャリアカウンセラーやエージェント
- 家族や友人(ビジネス感覚を持った人ならより◎)
これらの人たちに、今の状況や悩みを話してみましょう。
話すことで頭の中が整理されるだけでなく、「自分が本当に求めているものは何か」に気づける場合もあります。
重要なのは、「感情論だけで突っ走らないこと」。
辞めるのも続けるのも、どちらも選択肢です。
そのうえで、より後悔しない道を選ぶために、冷静な意見を受け取る場を持つことが、自分を助けることになります。
「自分ひとりで抱え込まないこと」。
これは、どんなに小さな悩みであっても共通して言える大切なポイントです。
客観的な意見を取り入れることで、焦りや不安に飲み込まれず、自分らしい決断をするための視野を広げていきましょう。
6. まとめ:離職率の数字に振り回されないために
新卒の離職率は確かに高いです。
でも、それはあなたの努力が足りないからでも、わがままだからでもありません。
社会の変化や企業側の問題、働き方の多様化——
さまざまな要因が絡み合って、今の現状があるのです。
大切なのは、「自分がどう感じているか」。
統計やクチコミも参考にしつつ、最終的には自分の感覚を信じて、未来を選び取りましょう。辞めることも、転職することも、キャリアにおいて立派な選択肢のひとつです。
焦らず、自分らしい一歩を踏み出していきましょう。
🌟 エイトリンクで働く魅力
✔ 未経験OK! 実践的なWebマーケティングスキルを学べる
✔ 成果を評価! 若手が活躍できる環境
✔ 営業×WEB制作 どちらの道も選べる